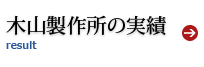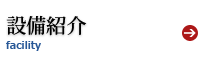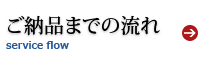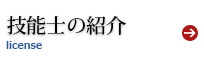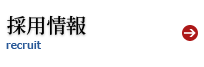「ネットワークの時代」の記事一覧
めっちゃハジッコ【機械要素展】
19日水曜日から、機械要素展、出ます。
でも、めっちゃハジッコ(;”∀”)

いっちばん奥じゃん。
誰か来てくれるかなぁ…
こんな感じ。

明日の準備日は雨ということで、今日のうちに車に積み込みます。

3日間とも立ってます。
ヒヤカシに来てね\(^o^)/
惚れてまうやろ、松戸市
本社がある千葉県松戸市。
設備投資に補助金を出していただけるので、すっかり常連さん的に利用させていただいています。
感謝です。
大切な市民の税金ですから、仕方ないのですが、毎回15点の書類を提出します(;’∀’)
謄本などのたぐいも有りますが、事業計画~簡単な書類含め、10点は作成する必要があります(;´Д`)
仕方ない、仕方ない…

何度も修正をやり取りし、出来上がった書類をすべて印刷して、ハンコ押して、書類の束を持っていく。
そこまでが、申請の手順。
しかし今回、劇的な変化がありました。
これら書類の内容は変わらないのですが、
①押印は必要なくなりましたので、
②これまで確認のためメールで送っていただいた書類を、こちらで印刷して使います
③抜いていた日付は、最終の提出書類に合わせて、こちらで入力します
④送っていただくのは、謄本と市税滞納無しの証明、だけで結構です
キャー\(*^▽^*)/
なんて男前な対応♡
惚れてまうやろ、松戸市役所の対応!

どうやって食べようかなぁ(^o^)
台湾の取引先から、今年も立派なマンゴーを送っていただきました。
めっちゃテンション上がります\(^o^)/

台湾から送られてくる製品の受け入れ検査を行うのは、検査・物流グループのメンバー。
今回は彼らに優先的に配りました。
で、余ったモノものを、事務所で一発真剣勝負の大くじ引き大会。
普段から行いが良い私は、幸運の女神を引き当てました\(^o^)/

どうやって食べようかなぁ。
生ハムで巻いて、冷やしたカリフォルニアの白ワインかなぁ…(^-^)
濃い目に入れた鉄観音茶で、ストレートにいただこうかなぁ…(^o^)
あ、貴腐ワインあったから、ブルーチーズと一緒にいただこうかなぁ…(^.^)
金曜の夜を楽しみます。
ありがとうございました。
- 2024.06.27
- 会社のダメなところ
- 2024.06.21
- 機械要素展 楽しい\(^o^)/
- 2024.06.17
- めっちゃハジッコ【機械要素展】
- 2024.06.03
- 5000円で何する?season4 第11回
- 2024.05.20
- 撮影が入りました
- 2024.05.17
- 事故の可能性
- 2024.05.01
- 5000円で何する?season4 第10回
- 2024.05.01
- 聞きたいこと、とは
- 2024.04.30
- 24春の陣
- 2024.04.01
- 5000円で何する?season4 第9回
- 2024.03.15
- 春 受賞
- 2024.03.07
- 新人さん11トン
- 2024.03.01
- 5000円で何する?season4 第8回
- 2024.02.08
- 三×三
- 2024.02.07
- 10人/50万人
- 2024.02.05
- お湯割り
- 2024.02.01
- 5000円で何する?season4 第7回
- 2024.01.06
- 普通にスタート
- 2024.01.05
- 5000円で何する?season4 第6回
- 2023.12.28
- フィルター掃除
木山製作所のスタッフブログです
モノ作り集団「K製作所」の活動も随時更新中!
デザフェス等イベント出展情報もこちら
- 2024.07.08
- CADによるモデリング
- 2024.07.01
- 削り出しトルメキア軍コルベット製作風景3
- 2024.06.24
- 削り出しトルメキア軍コルベット製作風景2
- 2024.06.20
- ものづくりワールド東京2024
- 2024.06.12
- 削り出しトルメキア軍コルベット製作風景1
- 2024.05.27
- 削り出しトルメキア軍コルベット
- 2024.01.06
- 2024
- 2022.12.28
- トルメキア軍戦列艦を作る ~完成編~
- 2022.12.26
- トルメキア軍戦列艦を作る ~ウェザリング編~
- 2022.12.02
- MEMORIAL TABLET
- 2022.11.21
- トルメキア軍戦列艦を作る ~塗装編~
- 2022.11.11
- JIMTOF2022
- 2022.11.09
- トルメキア軍戦列艦を作る ~組み立て・表面処理編~
- 2022.10.21
- トルメキア軍戦列艦を作る ~3Dプリント編その2~
- 2022.10.14
- トルメキア軍戦列艦を作る ~3Dプリント編その1~
- 2022.10.12
- ものづくり部(仮)始動!
- 2022.10.04
- トルメキア軍戦列艦を作る ~モデリング編~
- 2022.09.30
- 3Dプリンターの可能性
- 2022.09.05
- ブラックバスフィギュア その2
- 2022.08.31
- ブラックバスフィギュア その1